

コラム記事
- ホーム
- コラム
-
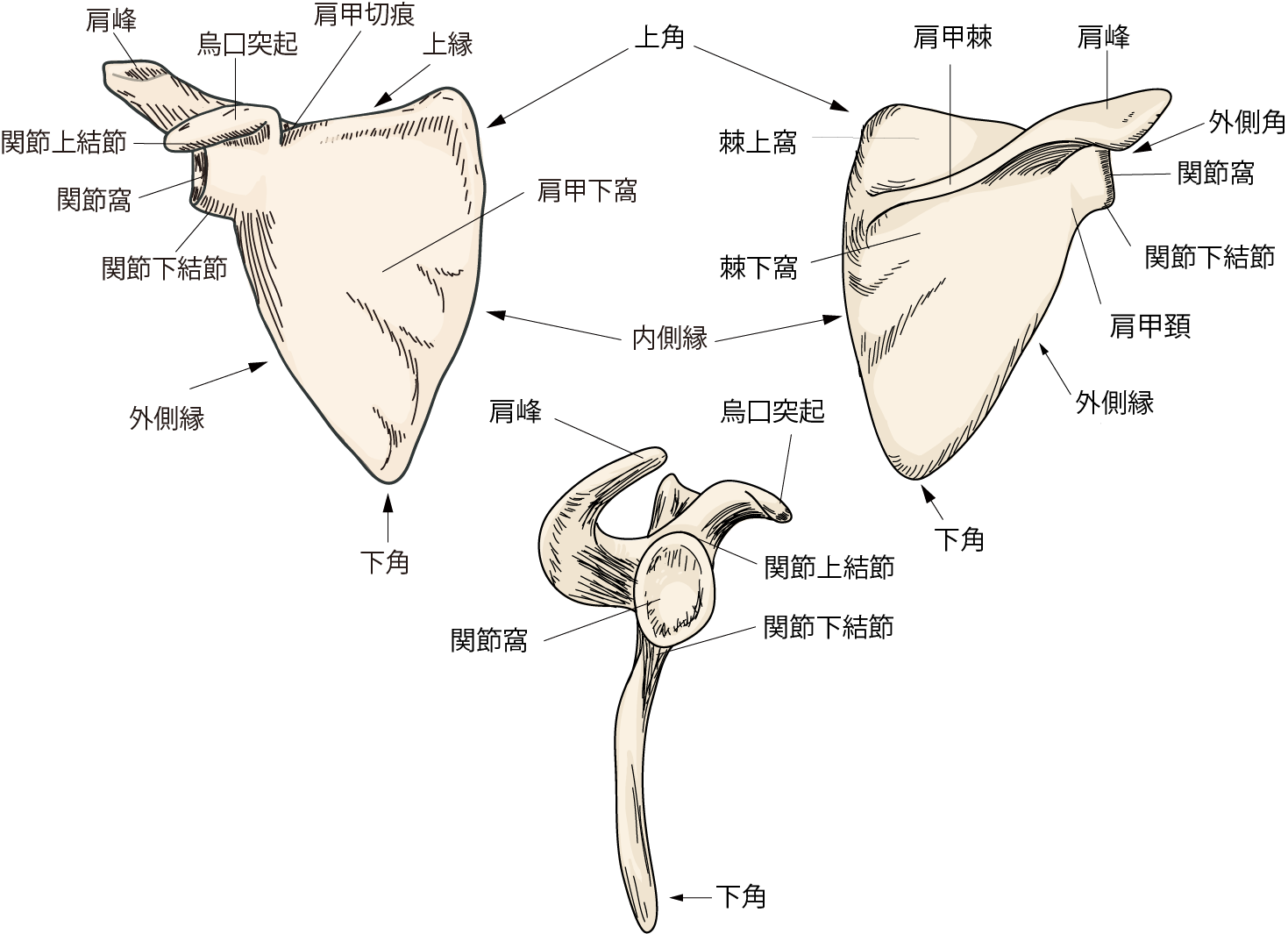
2020.11.19
肩甲骨骨折で認められる等級と認定のポイント
肩甲骨骨折は比較的まれな外傷とされていますが、その多くは...
その他のお怪我
上肢(手・腕・肩)
後遺障害
-
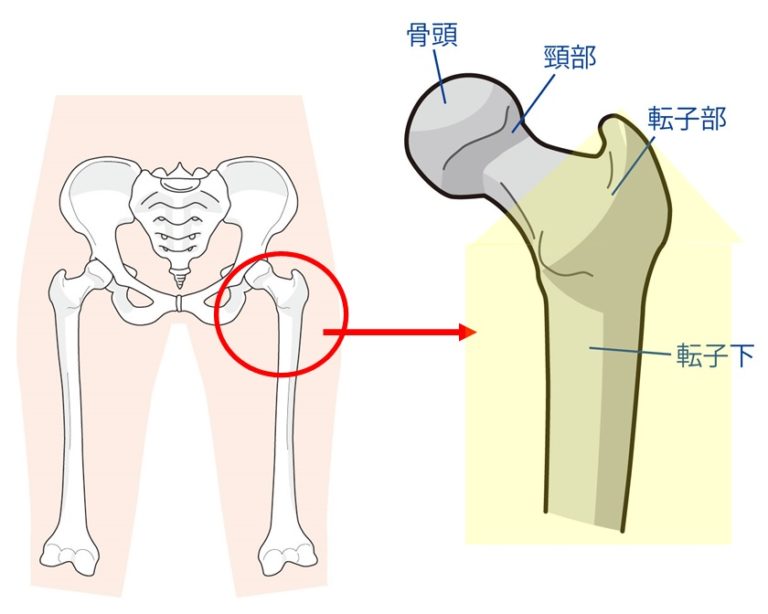
2020.07.08
大腿骨骨折で認められる等級と認定のポイント
交通事故で大腿骨を骨折するケースとして、歩いて横断歩道を...
下肢(足・膝・股関節)
後遺障害
-
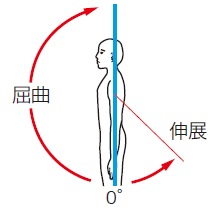
2020.06.01
上肢障害が後遺障害として認定される条件
上肢とは、肩関節から指先までの腕全体のことを指します。 ...
上肢(手・腕・肩)
後遺障害
-

2020.05.25
交通事故被害で弁護士に相談する時の費用の相場は?
交通事故の弁護士費用 交通事故被害に遭ってしまった。自分...
弁護士
費用
-

2020.04.23
交通事故で認められる顔周辺(目・耳・鼻・口)の後遺障害
交通事故で傷害を負ってしまい、顔の周辺に後遺障害が残って...
顔(目・鼻・口)
後遺障害
-

2020.04.06
脳外傷・高次脳機能障害に遭った方へ
交通事故で脳外傷を負った方・ご家族の方へ ~早期に弁護士...
高次脳機能障害
頭部
事故直後
ご家族向け
カテゴリー
おすすめ記事
CONTACT
交通事故に関するご相談は
初回無料です。
まずはお気軽に
お問い合わせください。
 0466-53-9340
0466-53-9340
[受付時間] 平日9:00-19:00
[相談時間] 平日9:00-21:00
 ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせ


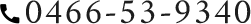





 初回相談無料
初回相談無料